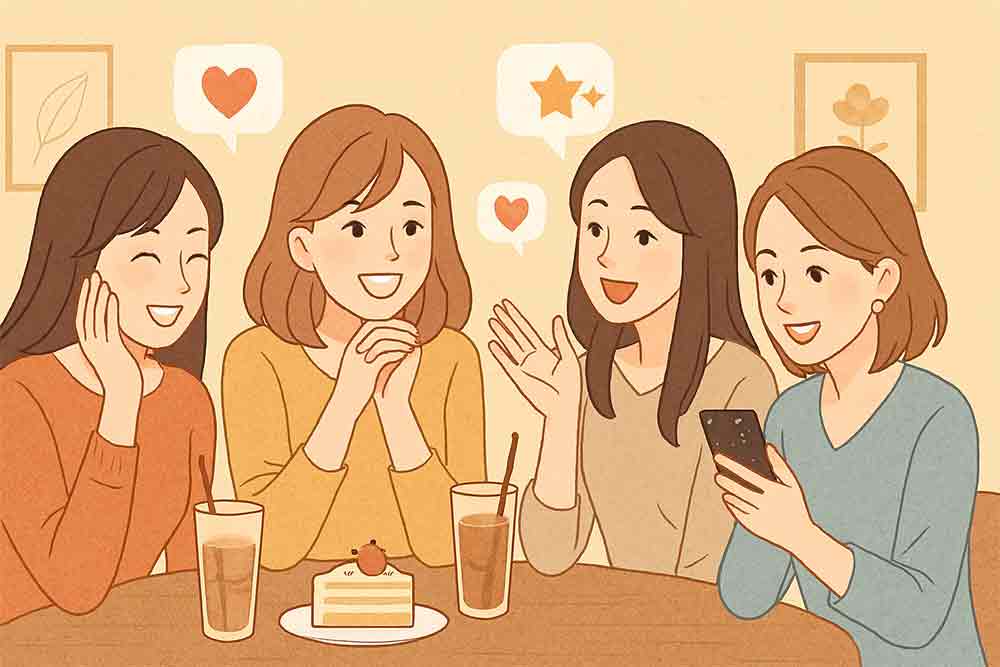遠軽駅を「ただの乗換駅」として通過するのは非常に勿体ない
「北海道&東日本パス」で北海道を旅をしているとき、遠軽駅は多くの旅人にとっては「ただの乗換駅」として扱われがちだ。
旭川から北見や網走方面へ、あるいは網走や北見から旭川方面へ行くとき、遠軽駅では改札から一歩も出ることもなく、隣のホームで列車に乗り継ぐだけ。そんな経験をしたことのある旅人も多いだろう。
だが、それは“鉄道ファン”の旅の仕方としては、あまりにも味気ない。遠軽という街は、北海道の鉄道の歴史そのものと言ってよいほどに、鉄道とは切り離せない濃厚な歴史を持つ場所なのである。
かつて激しい誘致合戦が繰り広げられた遠軽駅

最盛期は279人もの職員を抱えていたほどの遠軽駅
遠軽駅が開業したのは大正4年。平成27年には開駅100周年を迎えた。
鉄道の到来は、遠軽という街の発展を決定づけた大きな転機だった。北見から湧別へ伸びた湧別線が最初に開通し、続いて昭和2年には旭川から伸びる現在の石北本線が到達したことで、遠軽は複数の路線が交わる分岐駅となった。これが遠軽の街が交通の要衝として栄えるきっかけとなる。
分岐駅の座を巡っては、遠軽駅と安国駅の間で激しい誘致合戦が繰り広げられた。地元の開拓者たちは、自らの土地を鉄道用地として差し出し、私財を投げ打ってまで鉄道を呼び込もうとした。彼らの執念が遠軽駅を分岐駅へと押し上げたのである。
開拓期から交通の中心として街を支えてきた遠軽駅は、現在も石北本線の主要駅として網走駅、北見駅に次ぐ乗客数を誇り、地域の生活を支え続けている。このことから、遠軽という街は鉄道の歴史そのものとも言えるのだ。
遠軽駅は複数路線が交差するターミナル

遠軽駅に停車するJR北海道H100形気動車
普通の途中駅であれば、線路が一直線に貫き、構内もコンパクトにまとまる。しかし、遠軽駅の風格は趣が異なる。
構内は広く、線路は曲がり、分岐が多く、どこか“整理役”を任されていたような雰囲気が漂う。これは遠軽駅が複数の路線をまとめる機能を担ってきた歴史を物語っている。
かつて、遠軽駅は「旭川方面」「北見・網走方面」「湧別(オホーツク沿岸)方面」という、目的も性格も、線路の規格すらも違う、異なる三方向の鉄道路線が集まっていた。これらは同じ一つの計画のもとに建設されたわけではない。地形、予算、政治、地域事情といった複数の要因の中で、結果として遠軽に路線が集まったのである。
遠軽駅名物の平地スイッチバックは名寄本線の名残

遠軽駅でスイッチバックする石北本線の線路(2016年撮影)
遠軽駅と言えば、スイッチバックを思い浮かべる人も多いだろう。鉄道に詳しくない人からすると「なんで方向転換するの?」と不思議に思える構造だ。遠軽駅では列車が一度駅に入り、進行方向を逆にして次の駅へと走り出す。
スイッチバックは急勾配を上るために山岳地帯の鉄道に採用されることが多い仕組み。しかし、遠軽駅のスイッチバックは地形の問題で生まれたわけではなく、全国でも珍しい「平地スイッチバック」となっている。それは、かつて遠軽駅が「名寄本線」という別ルートの起点だったことを理由とする。
名寄本線は1989年に廃止されたが、2025年現在としては「本線」を名乗るJR線で唯一全線が廃止となった路線でもある。名寄本線は名寄からオホーツク沿岸を経て遠軽へと至る路線で、石北本線が開通する前は、旭川から遠軽や北見、網走方面へと向かう主要ルートであった。
平地にも関わらずスイッチバックが採用されたのは、後から作られた石北本線を無理なく接続するためである。名寄本線が廃止された今も、遠軽駅の線路配置はその記憶を静かに伝えてくれる。
遠軽という街が見せる静かな旅の風景

近隣のオホーツク海やサロマ湖が育んだ新鮮な海産物を食べられるのも魅力
遠軽を鉄道で素通りする旅人の多くは、次の列車の時刻だけを気にしてホームに佇む。
だけど、ほんの少し勇気を出して改札を抜ければ、この街は思っていたよりも深く、静かで、豊かな表情を見せてくれる。鉄道がつくった街の骨格の上に、地形と季節がゆっくりと風景を重ねてきた。
せっかく長い旅路を経てここまで来たのなら、街を散策したり、一泊して夜の静けさに身を置いてみてほしい。ホームに立つだけでは気づけない、この土地ならではの深い魅力が姿を現してくれる。
瞰望岩が語る街の原点

頂上は無料の展望台として(夏場は)気軽に訪れることができる
遠軽の中心にそびえる瞰望岩(がんぼういわ)は、この街の象徴であり、鉄道で遠軽に近づく旅人が最初に出会う“街の顔”でもある。
地上約78メートルの岩壁は、鉄道が来る前からここに立ち続け、遠軽という土地を体現してきた存在だ。岩の上から見下ろす街並みには、地形が先にあり、そこへ人が寄り添い、やがて鉄道が線を引いたという、この土地の歴史の順序がそのまま刻まれている。
丘に咲くコスモスと現在進行形の物語

コスモス園は街の大きなイベントが開かれる文化の発信地でもある
太陽の丘えんがる公園のコスモス園は、遠軽が自然とともに生きる街であることを静かに示している。10ヘクタールの斜面に広がる1,000万本のコスモスは、風に揺れるたびに丘全体を色彩の波に変える。鉄道が街をつくり、街が人を呼び、そして人が花を植え、また新しい風景が生まれていく。
道の駅がつなぐ遠軽の“今”

新しい観光名所として取り上げられることが多い道の駅
道の駅「森のオホーツク」は、鉄道とは別のリズムで旅人を迎える。車で訪れた人々がエンジンを止めると、スキー場から吹き下ろす風が静かに流れ込み、遠軽の“今”の空気を運んでくる。オホーツクの自然と人の暮らしが混ざり合い、鉄道とは違う角度からこの街の輪郭を見せてくれる。
木材が語る遠軽の文化と記憶

ちゃちゃワールドは遠軽駅から20分ほどの生田原駅の近くにある
遠軽の観光は「木」という素材を通しても語られる。木楽館では木工品が展示され、ちゃちゃワールドには世界各地の木のおもちゃが並ぶ。木材加工はこの土地の産業であり、文化であり、記憶でもある。木に触れることは、遠軽の時間に触れることでもあり、開拓の時代から続く“森との共生”を静かに思い起こさせる。
“鉄道ファン”に寄り添う遠軽町のお勧めホテル
鉄道の歴史と共に歩んできた街だけあって、駅の周辺に地元のホテルが点在している。
客室にもよるが窓から鉄道のある風景を眺めることができたり、きっと“撮り鉄”の鉄道ファンに寄り添ってくれることであろう。
遠軽駅すぐの「タカハシイン」
駅を出て最初の大きい通り「岩見通り」を左に曲がってすぐの所にある。遠軽中心部では大きいホテルで、都市部のビジネスホテルと同じような感覚で利用できるのは、初めてこの地に宿泊する人には安心ポイントとなるだろう。
生田原駅すぐの「ノースキング」
同じ遠軽町内で遠軽駅から普通列車や快速列車で約20分のところにあるのが生田原駅。宿泊者は無料で利用できる温泉もあり、レストランや休憩コーナーなども充実しているホテル。日帰り入浴も利用できる。
一本の列車を見送るだけで始まる“本当の旅”

遠軽駅は「ただの乗換駅」として通過するのは勿体ない駅である
遠軽は“通過する街”ではなく、“降りて歩くべき街”だ。
次の列車を一本見送るだけで、旅の速度はゆっくりと変わり、街の時間があなたの旅に溶け込んでいく。瞰望岩の影、コスモスの丘、森の静寂。どれも急ぎ足では見えない風景だ。遠軽は、旅人が立ち止まることで初めて本当の姿を現すだろう。