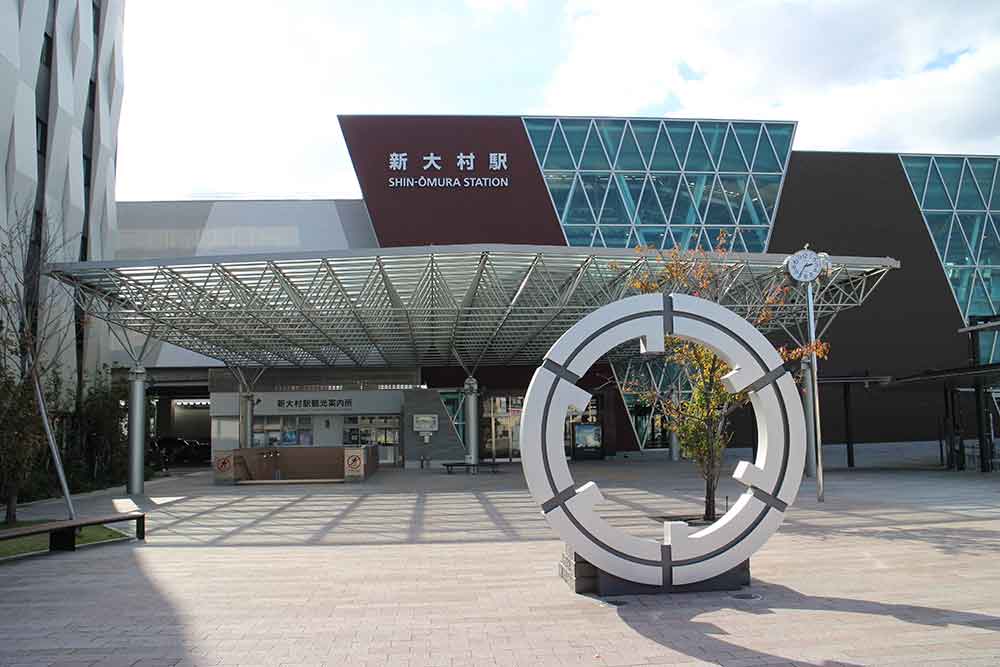観光地には語るべき風景が必要だ。語られるに値する物語、あるいは語られなくとも沈黙の中に何かが宿る風景。
だが、佐世保観光のメジャースポットとされる九十九島遊覧船には、そのどちらもなかった。佐世保に来たついでに乗ってみたが、10分で飽きた。いや、正確には出航して数分で「これはダメだ」と思った。島がある。ただそれだけ。風景が語りかけてこなかった。
島の数だけが記憶に残った

九十九島遊覧船パールクィーン
白くて優雅な船体。真珠雑貨のショップ。バリアフリー構造。展望デッキには特別室もある。九十九島遊覧船「パールクィーン」は、見た目と設備だけなら“整っている”。定員280名、所要時間約50分、料金は大人2,200円。スペックは申し分ない。だが、問題はその“中身”だった。
船は静かに進む。208の島々が並ぶ。それだけ。島の形に物語があるわけでもなく、風景に仕掛けがあるわけでもない。解説は控えめで、演出は皆無。風景は沈黙し、時間だけが過ぎていく。50分漂った末に残ったのは、「島が多かったな」という感想だけだった。それは揺れ動いた心ではなく、ただの情報だった。
乗客たちは風景から目を逸らし始めた
船が出航して20分経った頃には、乗客の何人かは島々を背にした。指先はスマホを滑り、目線は通知に吸い込まれ、会話は海とは無関係のものになっていた。船は確かに進んでいたが、乗客の関心はすでに別の所にあった。
それは彼らの怠慢ではない。反応する余地がなかったのだ。どこが見どころなのか、なぜこの航路なのか、何を感じてほしいのか。そうした“語りかけ”がないまま、船は進む。旅人の感性に投げかけてくるものがない。
結果、乗客は島々の景色を自分の時間に塗り替える。スマホ、雑談、瞑想。風景に向き合う理由がなければ、目の前の海はただの背景に変わる。208の島々は、十分な関心を寄せられないまま、通り過ぎていく。
長く感じる50分、薄く感じる体験

九十九島遊覧船の所要時間は約50分。一見すると「たっぷり楽しめる」と思わせる数字だが、実際に乗ってみるとその長さが裏目に出る。風景に変化が乏しく、演出も控えめ。乗客はただ海を漂うだけで2,200円。体験としての密度が薄いまま、時間だけが過ぎていく。
あるクチコミには「20分で1,000円にしてほしい」という声もある。これは単なる価格交渉ではなく、体験の本質を突いた批判だ。退屈な時間を長く引き延ばすより、短くして濃くする方が誠実である。50分という設定は、体験の質を薄めているようにも思える。
比較対象として思い出すのは、網走の流氷クルーズ。高波などで航路が短縮される場合は、料金が半額以下にまで下がる。体験の質が下がるから安くする、という誠意が感じられる。流氷が見られない可能性が高い場合には、事前にその可能性が告知された上で、客は乗船するかどうかを選択することができる。
もし、この九十九島遊覧船が20分で1,000円だったなら、乗客は「短かったけど、まあこんなものか」と納得できたかもしれない。だが、50分という長さが“退屈”を強調し、価格が“期待”を裏切る。この設計は、旅人の体験を重視するものではない。
海きらら? 水族館らしさという既視感

九十九島遊覧船のチケットを提示すると近隣の水族館「海きらら」に割引価格で入館できる。セットで回ればお得、という設計らしい。だが、その水族館が本当に“行く価値のある場所”かどうかは別の話だ。
海きららはクラゲやイルカ、九十九島の海の生き物を展示する水族館。パンフレットには「九十九島の自然を感じられる」とあるが、展示構成や演出は全国どこにでもある水族館と本質的には大差ない。クラゲの照明演出、イルカのショー、生き物体験コーナー。自分にしたら既視感の連続。“水族館らしさ”をなぞっている印象が強い。
新潟のマリンピア日本海の年間パスポートを持つ自分にとって、こうした“どこにでもある水族館”は通過点でしかない。割引制度は体験の価値を高めるための仕掛けではなく、売上を伸ばすための導線にすぎない。遊覧船と水族館をセットにすれば、観光客は半日くらいは過ごせる。だが、薄い体験を二つ重ねても、観光地としての満足感は感じられないだろう。
陸地の周辺施設に漂う時代錯誤感

九十九島遊覧船の乗り場周辺には観光客向けの飲食店や土産物屋が多いが、観光地としての“開かれた感覚”が欠けていた。
例えば、土地の名物を提供する飲食店。「店内が狭いためベビーカーのご利用はご遠慮ください」「静かにお食事されたい方のために配慮をお願いしています」といった類の文言が店のサイトに並ぶ。直接的な拒否ではない。だが、読み手には十分伝わる。「子連れは歓迎しない」「むしろ来るな」という空気が、遠回しに、しかし確実に伝達されてくる。表面的には丁寧だが、実質的には選別だ。
そしてこれは、たまたまその店だけの話ではない。佐世保市内を歩いていても、似たような空気を感じる場面が多かった。店の雰囲気、掲示の文言、接客のトーン。どれも「来てほしい人だけ来てくれればいい」という姿勢が滲み出ている。観光地としての“開かれ方”よりも、“馴染み客の快適さ”を優先する構造が、街のあちこちに埋め込まれていた。
島の数だけが記憶に残る静かな終わり
九十九島遊覧船は、旅の顔をしていた。白く塗られた船体、展望デッキ、パンフレット、水族館とのセット割引。すべてが「観光地らしさ」を演出していた。だが、50分間の航行で得られたものは、208という数字だけだった。
旅人は語りのない海を漂いながら、静かな海を後にした。